はじめに
毎年、夏の登山シーズンになると、富士山には国内外から数多くの登山者が訪れます。
しかし、実際に登頂できる人の割合は70〜80%程度と言われています。
その理由の一つは、富士山特有の厳しい自然環境です。
山の天気は変わりやすく、急な悪天候による下山を余儀なくされることがあります。
また、標高3,776mの富士山では標高が上がるにつれ空気が薄くなり、体調不良を引き起こすリスクが高まります。その中でも特に多いのが「高山病」です。
悪天候は避けられない部分もありますが、体調不良、特に高山病による下山はできる限り防ぎたいものですよね。
そこで今回は、富士山に複数回登った経験を持ち、さらに富士山診療所で医師として勤務したことのある筆者が、高山病にならないための実践的な対策10選をご紹介します。
かくいう私も富士山診療所での勤務の際には、自分自身が高山病の症状に悩まされました。
しかし、今年の富士登山ではしっかりと対策を実践したことで、高山病になることなく無事に登頂を果たすことができました。

今年の富士登山シーズンも残りわずかですが、これから富士登山を予定している方にとって役立つ内容になっているはずです。
ぜひ参考にして安全で快適な登山を楽しんでください。
高山病とは
高山病とは「酸素濃度の低い高地環境に体がうまく適応できないことで起こる疾患」です。
代表的な症状としては、吐き気、嘔吐、倦怠感、頭痛、めまいなどが挙げられます。
一般的に、高山病は標高2,500m前後から発症リスクが高まると言われており、標高3,776mの富士山では多くの登山者が影響を受けやすい環境となっています。
実際に私が富士山診療所で勤務した際も、来院される患者さんの約8割が高山病の方でした。
また、診療所に来るほどではなくても、登山中に「生あくびが増える」「手足のしびれや筋肉のコリを感じる」「軽い頭痛がする」など、高山病の初期症状が出ている方は多いです。
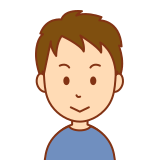
私は指先や顎先のしびれ、鼻の奥がツーンと痛むような症状が出ました。
そのため、高山病は誰にでも起こり得るものと理解した上で、事前にしっかりと対策をしておくことが大切です。
高山病対策 10選
①荷物はできる限り軽量化する
富士山の登山道には(山小屋も含め)ゴミ箱がありません。
つまり、自分が持って行った荷物は登山開始から下山まで全て背負う必要があります。
重い荷物を背負うと呼吸数や脈拍数が上がり、高山病のリスクを高めます。
そのため少しでも荷物を減らす工夫が必要です。
「山頂でコーヒーを沸かして飲みたい」「カップラーメンを作って食べたい」と思うかもしれませんが、バーナーやクッカー類を全て持ち運ぶと荷物が一気に重くなります。
多少割高にはなりますが、山小屋でコーヒーやラーメンは販売されているため、特に初心者の方は、荷物を軽くして快適に登ることを優先しましょう。
②水やお茶だけでなく、経口補水液を持参する
富士山=涼しいというイメージがありますが、日中の登山中は暑さを感じ、汗をたくさんかきます。汗とともに体内の水分だけでなく、ミネラルも失われます。
そのため、水やお茶だけでなくOS-1などの経口補水液を持参し、こまめに少しずつ補給しましょう。
ただし、水分を持ちすぎると荷物が重くなるため、過剰に持っていく必要はありません。
私見ですが、水分は1~1.5L程度を持参し、不足分は山小屋で補給するのがバランスの良い量だと考えます。
③酸素缶は持って行かない
富士登山では休憩中に酸素缶を吸っている人をよく目にします。
確かに高山病は酸素不足によって起こるため、酸素を吸入することで一時的に症状は改善します。
しかし、市販の酸素缶は酸素量がわずかで根本的な解決にはならない上に、高地順応を妨げてしまう可能性があります。
さらに、酸素缶は使用後に小さく折りたたむこともできず、下山までゴミとして持ち運ばなければなりません。
酸素缶に頼るのではなく、酸素缶が不要なペースでゆっくり登ることが何よりの高山病対策です。
④登山前日はしっかり眠る
睡眠不足の状態で登山をすると、高山病のリスクは非常に高くなります。
特に山小屋では、慣れない就寝時間や寝具、さらには酸素不足による息苦しさのために、ぐっすり眠れないことも少なくありません。
そのため、登山前日にしっかり睡眠を確保しておくことが重要です。
登山当日は早朝に自宅やホテルを出発する人も多いため、前夜はできるだけ早めに布団に入り、十分な休養をとるように心がけましょう。
⑤5合目に着いたら最低1時間は滞在する
多くの方はバスやタクシーで富士山5合目までアクセスするかと思いますが、到着してすぐに登り始めるのはNGです。
富士山5合目はすでに標高2,000mを超えており、体は低地とは違う環境にさらされています。
本来、高地順応には数日かかるため、数時間程度の滞在で完全に慣れることはできません。
それでも、到着後に最低1時間は滞在することで高山病に多少は備えられます。

5合目には売店やレストランが併設されている場所もあります。
軽食をとったり、景色を楽しんだり、軽く準備運動をしたりしながら時間を過ごし、体をゆっくり高地環境に慣らしていきましょう。
⑥登山中は「歩幅を小さく、ゆっくり登る」
富士山は標高が高く酸素が薄いため、一度息が上がるとなかなか回復しません。
そのため、登山中は歩幅を小さく保ち、息が乱れないようにゆっくり登ることを意識してください。
後ろから早い登山者が来ると、つい自分もペースを上げてしまいがちです。
しかし、登山は競争ではありません。
無理にスピードを上げる必要はないので、早い人には道を譲り自分のペースを守りましょう。
⑦休憩時には深呼吸を意識!口すぼめ呼吸も有効
登山中は無意識のうちに呼吸が浅くなり、酸素不足に陥りやすいです。
そのため、休憩の際には意識的に深呼吸をして体に酸素を取り込むことが大切です。
さらに有効なのが「口すぼめ呼吸」です。
これは、息を吐くときにロウソクの炎を消すように口をすぼめてゆっくり吐く方法です。
この呼吸法を行うことで、肺に残る空気(機能的残気量)が減少し、一度に取り込める酸素量が増えます。
結果として呼吸困難をやわらげ、高山病の予防にもつながります。
⑧宿泊は標高の低い山小屋を選ぶ
富士登山では「ご来光を見たい!」という理由から、標高の高い8合目や本8合目の山小屋に宿泊する方が多いです。
しかし、高山病は睡眠中に悪化しやすいです。
睡眠中は呼吸が浅くなりやすく、その結果、酸素不足が進んで高山病の症状が強まります。
実際、私が富士山診療所に勤務していたときも、夜間に高山病の患者さんが多かったです。
そのため、高山病対策の点からは、標高が低めの7合目以下の山小屋に宿泊することをおすすめします。
⑨ツアーガイドのペースに合わせる
多くの登山者は、ご来光を見るために深夜から山頂を目指します。
しかし、頂上が近づくにつれて登山道は混雑し、焦ってペースを上げてしまいがちです。
そこで、もし近くにツアー集団がいる場合は、ツアーガイドのペースに合わせて登るのもおすすめです。
ツアーガイドは富士登山のプロであり、参加者が無理なく登れるように最適なペースで歩き、ご来光に間に合うように時間配分をしています。
無理に自分のペースを乱すより、ガイドのリズムに合わせて登ることで安全性も高まります。
もちろん、ツアーの邪魔にならないことが大前提ですが、後方からついていくのも良い方法でしょう。
⑩高山病予防薬「ダイアモックス」の服用
ここまでご紹介した対策を実践すれば、多くの方は十分に高山病を予防できるでしょう。
ただ、それでも高山病が心配という方は、医師による処方のもとで「ダイアモックス」という薬を予防的に内服する方法もあります。

この薬は登山前日から服用することで高山病の予防効果が期待でき、登山中に高山病の症状が出た場合の治療薬としても使用可能です。
ただし、ダイアモックスは市販されていないため、必ず医師の診察と処方が必要です。
費用は自費で、数千円程度で、オンライン診療に対応しているクリニックもあります。
万全の準備をしたい方は、登山前に医師へ相談してみると良いでしょう。
まとめ
富士登山は日本一の山ならではの魅力的な経験ですが、厳しい自然環境のため体調を崩す人も少なくありません。
特に高山病は誰にでも起こり得るもので、症状が出ると登頂を断念せざるを得ないこともあります。
しかし、事前にしっかりと準備し、対策を取ればリスクを大きく減らすことができます。
今回ご紹介した10の方法は、どれも実践しやすいシンプルなものばかりです。
ぜひ登山計画に取り入れて、安心安全に山頂からの絶景を楽しんでください。




コメント